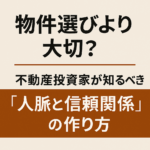先日、博報堂マーケティングラボが発表した『富裕層調査2025』をじっくり読みました。

数字を追うだけでなく、ライフスタイルや意識構造の変化まで丁寧に分析されたレポートで、
特に印象的だったのが、世帯年収3,000万円というラインが日本の新しい分岐点になっているという指摘です。
この調査では、年収1,500万円以上の層を「インカムリッチ(高所得層)」と定義し、その中でも3,000万円を超えると、意識・行動・価値観のフェーズが一段階変わるとしています。
読んでいて、「まさに現場で感じている変化と一致している」と思いました。
■ 3,000万円を超えると“稼ぐ人”から“資産を動かす人”へ
博報堂のデータでは、世帯年収1,500万円台で純金融資産1億円を超える家庭は2割前後。
ところが、世帯3,000万円を超えた瞬間にその割合は50%を突破します。
ここが、「給与で豊かになる人」と「資産で豊かさを維持できる人」の分岐点です。

また、職業構成も変化しており、年収3,000万円以上では経営者・役員層の比率が急増しており、キャリアの目標が「出世」から「自分の時間の使い方」へとシフトしていくのが特徴です。
このあたりは、私自身が経営者として共感する部分でもあります。
■ 教育と居住地選びは“投資判断”
博報堂のレポートを読んでいて特に共感したのが、教育を「投資」として考える姿勢です。
世帯年収3,000万円層では、「子どもの教育のためなら住まいも仕事も変える」と答える割合が高く、実際に受験や進学を機に港区から郊外、あるいはインターナショナルスクールの近くへ移る家庭も多い。
さらに、「子どもを海外留学させたい」と答えた割合は、世帯年収1,500万円層で35% → 3,000万円層で45%へ上昇。

教育意識の高さが、都市部の住宅市場や国際教育ビジネスを押し上げています。
この“教育ドリブンな住宅需要”は、デベロッパーとしても無視できないトレンドです。
■ タイパ重視の消費と「外注文化」
もうひとつ印象的だったのが、時間の使い方の変化。
年収が上がるほど、「家事・育児を外注する」傾向が強まっている点です。
家事代行、シッター、ドライバー、パーソナルトレーナーなど、自分でやるより“委ねる”ほうが合理的という考え方が一般化している。
博報堂の分析では、この層のキーワードは「タイパ(Time Performance)」。つまり、お金ではなく時間の効率を軸に生活を設計する。
住宅選びでも「通勤時間」「家事動線」「サポート体制」が重要視されるようになっており、家は“居住空間”ではなく“時間を最適化する装置”になりつつあります。
■ 健康・美容・ウェルビーイング=“自己資本”への投資
この層が共通して持つのが、「健康こそ最大の資産」という考え方です。
筋トレ、栄養管理、睡眠の質、美容医療への投資を当たり前とし、身体を“運用資産”として管理する感覚を持っています。
博報堂の調査でも、男性の美容支出が過去最高を更新。
「見た目」ではなく、「自己管理能力の象徴」として整える人が増えています。
これは不動産の世界で言えば、“建物の保守管理”と同じで、資産を長持ちさせるためのメンテナンスだといえます。
■ モノから「意味のある体験」へ
インカムリッチ層は、モノそのものより「ストーリー」や「体験価値」を重視します。
博報堂の調査でも、購買理由の上位に「心が豊かになる」「自分らしさを表現できる」が並び、高級車やブランドバッグよりも、旅行・アート・ワイン・学びへの支出が増えています。

この傾向は不動産にも通じます。
“どこに住むか”よりも、“どんな時間を過ごせるか”を重視する。
ラグジュアリーの定義が「空間」から「体験」へと変わっているのです。
■ 不動産会社経営者としての実感:家は「ステータス」から「戦略」へ
現場で感じるのは、年収3,000万円クラスの方々が家を「成功の証」ではなく、「生活戦略の一部」として買っているということです。
立地、動線、サポートサービス、教育圏、ヘルスケア施設のアクセス——
これらを総合的に組み合わせ、人生の時間効率を最大化するために家を選んでいます。
今後、住宅開発に求められるのは“快適な間取り”ではなく、時間・教育・健康をデザインした提案力。
これは、博報堂の調査が示す新しい富裕層像をそのまま裏づけていると思います。
■ まとめ:「3,000万円ライン」が描く日本の未来
博報堂の『富裕層調査2025』を読んで痛感したのは、世帯年収3,000万円はもはや“高収入”の象徴ではなく、生き方の転換点だということ。
この層の価値観は、「稼ぐ」より「時間をデザインする」ことに重点を置き、日本社会の消費・教育・住宅・サービス産業全体を動かしています。
静かに、しかし確実に——この“インカムリッチの時代”が、日本の都市構造と経済地図を塗り替え始めている。
それを肌で感じたレポートでした。