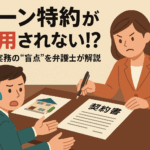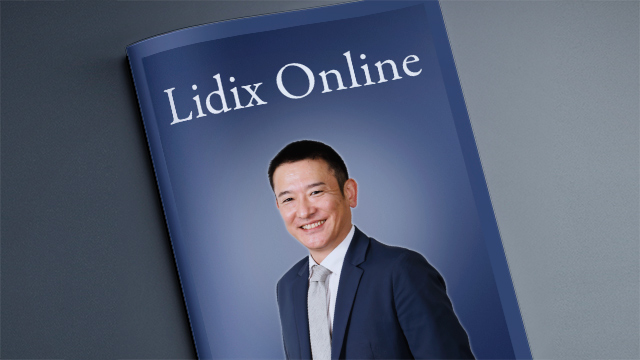【6件で逮捕】宅建免許ナシで物件売却…小規模投資家が知らずに越える“5つのライン”
「このレベルで捕まるとは…」――驚きと不安が広がった宅建業法違反事件。その背景には、意外な“思い込み”が潜んでいました。
INDEX(目次)
1. 事件概要:なぜ6件で逮捕に至ったのか
2025年春、ある不動産投資家が宅建業法違反容疑で逮捕・起訴され、罰金40万円の刑事処分を受けました。
問題視されたのは、2024年春にかけて行った6件の物件売却。いずれも資金繰り上の苦境を乗り切るためのものだったようですが、「免許なしで反復継続して売買をした」として刑事処分に。
※なお、刑事処分を受けると今後5年間、宅建業免許の取得・申請ができないという強い制限が課されます。
2. 「反復継続」のグレーゾーンとは?
宅建業法は、「業として宅地・建物の売買をする場合」に免許を求めています。
この「業として」がクセモノで、「何件ならOK」「何ヶ月以内ならセーフ」といった明確な数値基準は存在しません。
逮捕された投資家の場合も、以下のような背景があったとされています:
-
空き家賃貸業の一環として保有していた物件
-
思うように活用できずやむを得ず売却
-
転売ではなく、資産整理・資金確保が主目的
それでも、「6件でアウト」と判断されたわけです。
3. 空き家再生型ビジネスと宅建業の交差点
近年、地方や築古戸建を再生して賃貸運用する投資家が増えています。
-
1物件単価が安い
-
地方自治体の補助金・引取相談も多い
-
自社再生 → 状況により売却、という柔軟な出口戦略
こうしたモデルは件数が嵩みやすく、宅建業法との境界線が曖昧になりがちです。

特に「売却による資金回収」が継続的に生じる場合、知らず知らずに“宅建業”に該当してしまう恐れがあります。
4. 「業として行う」の5つの判断基準(行政実務上)
不動産業法務に詳しい辻田寛人弁護士によると、行政・裁判で「業」と判断されるかは次の5要素を総合的に見られます:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1) 取引対象者 | 親族や特定知人 → セーフ、広く一般向け → 要注意 |
| (2) 取引目的 | 利益目的だと「業」判断されやすい |
| (3) 取得経緯 | 転売目的の取得はアウト、自宅・相続等はセーフ傾向 |
| (4) 取引様態 | 自社で直接売る → 業性高い、仲介任せ → 緩和要素にはなる |
| (5) 反復継続性 | 複数回あるとアウト。具体的件数は非明示だが「6件」で逮捕された事例あり |
5. 私たちにできる予防策とは?
-
一線を越えそうなら、宅建業免許の取得を検討する
-
取引目的や相手を限定する(自己使用や親族間)
-
売却に至った理由・背景を記録・保存しておく
-
不動産弁護士や専門家に事前相談をしておく
-
トラブル回避を徹底する(通報が逮捕のきっかけに)
特に「反復継続していないつもり」でも、税務処理・登記履歴・資金の流れなどから「業」と見なされることがありえます。
6. 結論:「知らなかった」は通用しない時代へ
今回の事件は、「宅建業のボーダー」を超えてしまった投資家の実例として非常に示唆的でした。
-
空き家再生や築古転用は社会的にも有用な取り組み
-
しかし、制度が追いついていない現実がある
-
免許がなくても逮捕・処分されうる
法改正や指針の明確化が求められる一方で、投資家自身が「業」にならない売却スキームや相談体制を整えていくことが肝心です。