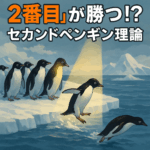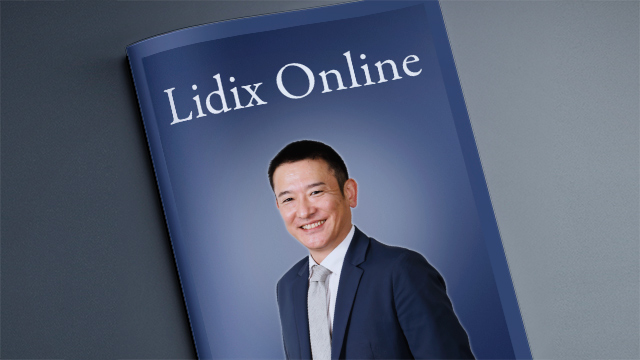サブリース契約を簡単に言うと、不動産の管理会社が物件を一括で借り上げる方式になります。
過去にはサブリース契約をめぐるトラブルもありましたが、賃料収入の変動リスクを抑えられるという点で、ちゃんと仕組みを理解すれば、個人の不動産投資においては採用の余地は“全然あり”だと思います。

まずはサブリース契約について、仕組みを正確に理解しておく必要があります。
世の中でよくいわれるサブリース契約は、正確には「マスターリース契約(特定賃貸借契約)」と「サブリース契約(転貸借契約)」の組み合わせで成り立っています。
マスターリース契約は、不動産のオーナーと管理会社間で締結する契約で、物件をまるごと管理会社に貸し付ける契約になります。
管理会社はオーナーに決められた賃料を支払う対価として、借りた物件を実際の入居者に貸し付ける権利を有します。
次に管理会社は、サブリース契約で実際の入居希望者に賃貸しをします。
管理会社は空室リスクも加味しながら、一般にオーナーへ支払う金額を上回る賃料を入居者から得るように、適切に賃貸経営を進めていきます。
サブリース契約のメリット
●賃料収入の変動を抑えらる
●入退去に関する費用が発生しない
●管理を一任できる
サブリース契約の最も重要なメリットは「空室による賃料収入の変動を抑えられる」ということになります。
個人の不動産投資において、毎月の安定した賃料収入を期待する人がほとんどです。賃料の変動リスクを抑えられるサブリース契約は、そのような投資家にとって魅力的な仕組です。
サブリース契約では、実質的に管理会社にアパート実務の全てお任せとなるケースが多いため、入退去や客付けの費用がかからないことも大きいです。
通常のアパート管理ではオーナーがコストを負担しなければならない退去時の原状回復や、入居者を募るための広告掲載など、全てが管理会社が負担する。契約内容によっては大規模修繕の時期までは、想定外のランニングコストが発生しにくい仕組みとなっています。
特に最近の募集広告などは、手数料を倍にするケースがほとんどなので、入退去が多いアパートなどはかなりの出費があります。
サブリース契約で運営しているアパートは何かしらの作業が発生することはなく、毎月の管理会社からの賃料が予定通り入金されているのを確認するだけですむため、サラリーマンなど、本業を抱えながら不動産経営をする人にとっては、大きなメリットがあるといえます。

サブリース契約の注意点
●保証料の引き下げリスクがある
●地域の賃料相場より安くなりがち
●入居者を選べない
多くのサブリース契約利用者が懸念しているのが、「保証賃料の引き下げリスク」ではないでしょうか。現在のサブリース契約のほとんどは、数年に1度程度契約が見直される仕組みになっています。
数年に一度の契約更新では、その物件の実態に従って保証賃料が見直される場合があります。もちろん上昇する可能性もありますが、基本的には空室率や経年劣化を加味して、保証賃料が下がる場合が多いと思います。
ただ、通常の賃貸経営でも、経年劣化や空室と共に賃料や収益性が下がるのは一緒です。変動が数年に一度で予見性が持てる方が良いと思ったほうが良いというような見方もありますね。
オーナーと管理会社間のマスターリース契約の賃料は、基本的にその地域の相場より安いか、あるいは管理料が高く設定されているケースが多いです。いずれにしても手残りが少なくなる仕組みになっています。満室の時期が長い物件であればサブリース契約にしない方が収益性は高いと思います。
一般的な賃貸管理の場合は、入居者審査の過程で、基本的にオーナーの意見も反映されます。入居希望者の信用情報や収入などに懸念材料があれば、断ることも可能です。
サブリース契約では、入居者の選定は完全に管理会社の裁量で進められます。
契約内容にもよりますが、オーナーは自分の物件にどのような人が住んでいるのか全くわからない場合も多いため、家賃滞納や物件の破損などのトラブルが起きたときに、入居者の審査に問題があったとしても、オーナーがそれを完全に把握するのは難しいでしょう。
サブリース契約で失敗しないためのポイント
- サブリース契約が自分にとって有効かを考える
サブリースが自分にマッチしているのかを考える必要があります。サブリース契約は、当面の収支を安定させる代わりに、収益性が「下がる」のが基本になります。
当たり前のようにリスクが下がればリターンも下がります。リスクを取ったり、物件管理で工夫したりして収益性を高めたい人には不向きといえます。
- 保証賃料の水準と諸費用の有無を確認する
サブリース契約込みの管理コストは、通常の物件管理より割高です。概ね10%~20%程度が保証料・管理料の目安であり、本来の物件の満室賃料の80%~90%がオーナーの収入となります。
10%と20%では収益性がかなり変わってくるので、管理コストの水準は精査する必要があります。
また、管理費用などの名目で別途徴収されるコストがあるかどうかのチェックも忘れずに。
- 賃料見直しの頻度を確認する
賃料は基本的に数年に一度見直されます。概ね2年~5年程度の周期となっている場合が多いですが、契約内容によって異なるのであからじめ確認しておきたいところです。
収益安定性の観点からは、周期は長い方が当然メリットが大きいといえます。
- 解約時のルールを理解する
サブリース契約の解約は、物件の売却時に重要な論点になります。サブリース契約では、管理会社が物件の「借主」となる。日本の法制度は、賃貸契約において借主の権利が尊重される傾向にあり、オーナー側からの契約解除のハードルが高いことを念頭に置く必要があります。
物件を売却するときには、既存のサブリース契約を解除するか、オーナー変更(新たなオーナーが契約を引き継ぐ)をする必要があります。契約の解除や変更の取り決めが整備されていないと、売却しづらかったり、後々トラブルになったりする恐れがあるので注意が必要です。
売却や契約変更の条件が過度に厳しい管理会社は、利用を避けた方がいいかもしれません。

サブリース契約については、過去にトラブルが発生した事例もあって不安を抱く人も多いかもしれません。しかし、契約内容が適切なものであれば、初心者が安定した条件で不動産投資に取り組むうえで、有効な手法の一つといえます。
「サブリースにすると収益性が下がるから」とよく耳にしますが、収支変動のリスクを抑制する以上、その代償として収入が落ちるのは自然なことです。
サブリース契約の特性を正しく理解したうえで、そもそも「当面の収支を安定させる」性質のある契約が自分に必要であるかを考えながら、利用の是非を検討する必要があります。