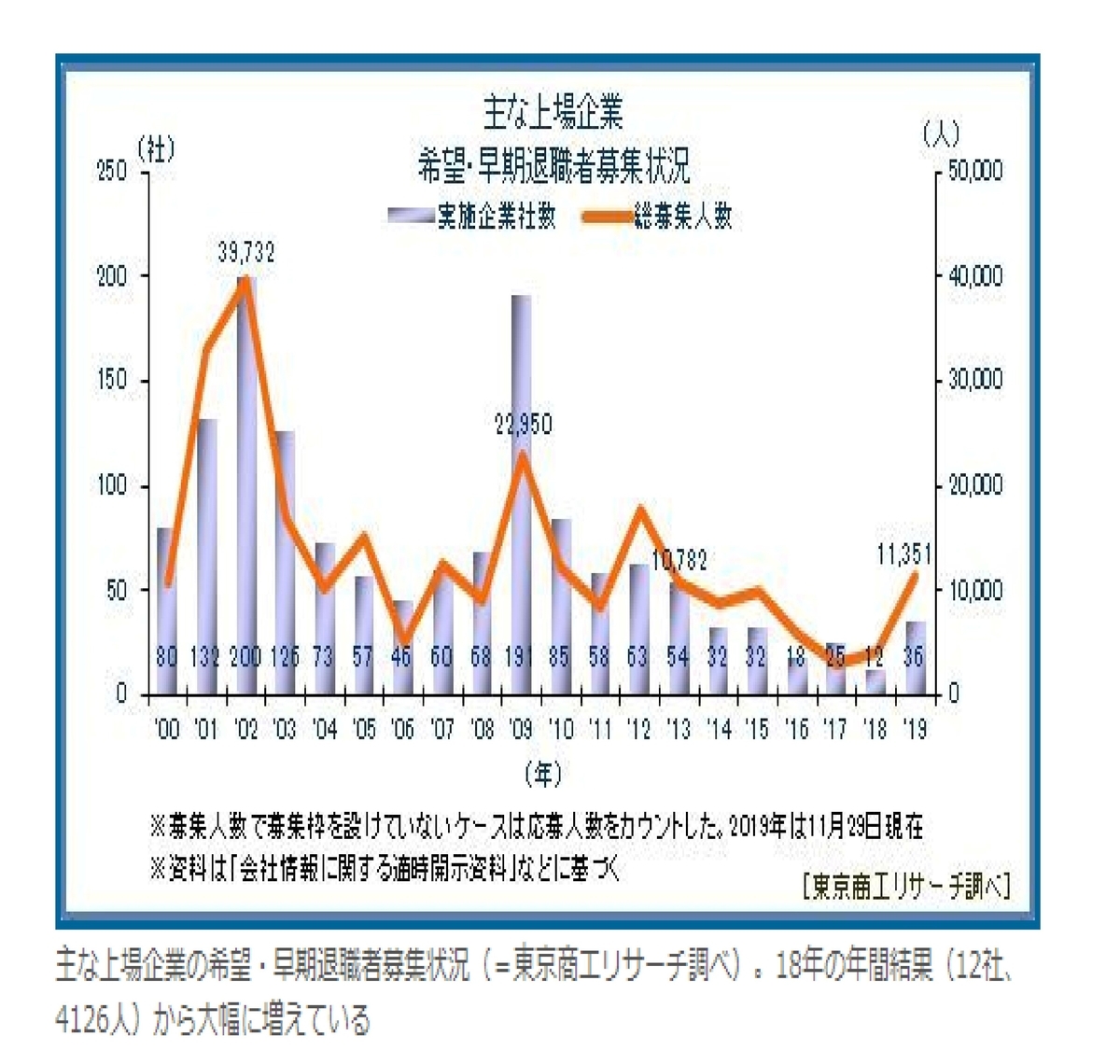年齢別の戦術論と「ワークライフバランス」という幻想
会社経営をしていると、20代の方から「ワークライフバランスを大事にしたい」という声をよく聞きます。
でも、正直なところ僕自身の経験から言えば、若い頃にバランスを取ろうとしても、何も残らないんです。
今回は僕がこれまでの仕事人生で感じてきた「年齢と働き方のリアル」について書いてみたいと思います。
20代は「体力を投下する時期」——量をこなした人しか技術は残らない
僕も20代の頃は、休みもほとんど取らずに現場を走り回っていました。
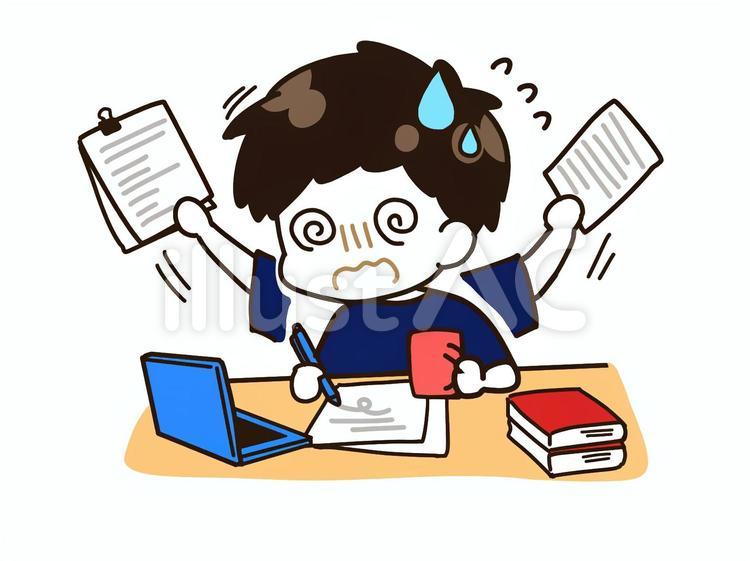
今振り返れば、あの“量の時期”がなかったら、今の判断力や技術は絶対に身についていなかったと思います。
20代の武器は、間違いなく「体力」です。
でも最近は“効率的に”“スマートに”仕事をしたいという風潮が強く、最初から「量より質」を口にする人が多い。
ただ、僕の実感で言えば、量をこなさなければ質は生まれない。
不動産でもそうです。
物件を何十件も現場で見て、数えきれないほど失敗して、やっと“見る目”が磨かれていく。机上では絶対に身につきません。
だからこそ、20代は「体力をぶち込む」しかないと思っています。
そしてこれが後から質を求めるための“下積み期間”になるのだと思います。
30〜40代は「技術と人脈」で勝負する時期
30代に入ると、仕事の勝ち負けを決めるのは“スキルと判断力”です。
そして40代に入ると、明らかに“人との繋がり”がすべてになってきます。
このフェーズになると、単純に働く時間を増やすより、
「誰と組むか」「誰と時間を使うか」の方が圧倒的に重要になります。

僕自身も40代を過ぎてからは、現場で汗をかく時間を少し減らして、信頼できる仲間や投資家、銀行、設計士さんと話す時間を増やしました。
結果として、それが一番“効率的”だったと思います。
若い時に走り切って“技術と実績”を積み上げていたからこそ、今は「働く時間を減らしても結果が出る」状態を作れたのだと思います。
ワークライフバランスの「バランスが悪さ」
僕は“ワークライフバランス”という言葉を聞くたびに、少し違和感を覚えます。
人生って、各年代で使える武器が違うと思っています。
20代も50代も同じように1日8時間働くのは、むしろバランスが悪い。
ボクシングで言えば、全ラウンド均等にパンチを出すのではなく、「ここが勝負どころ」という瞬間に全力を出すことが大事です。
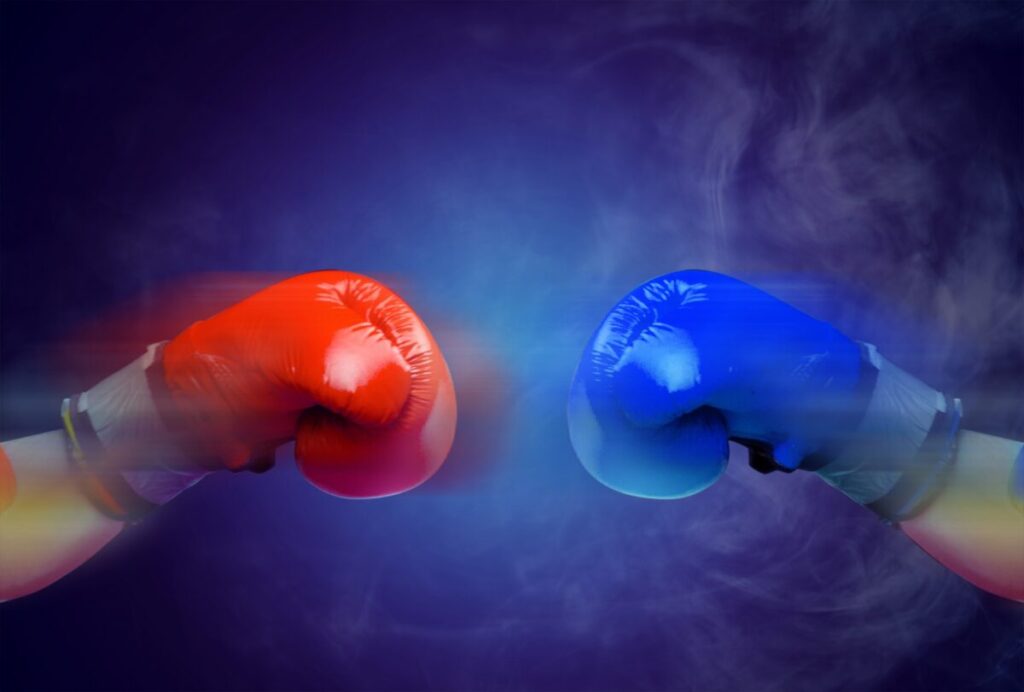
20代はまさに“全力で打ち込むラウンド”です。その勝負を避けて通った人は、後のラウンドで勝てない。
だから、20代で全力を出すことは、将来の“時間的自由”を手に入れるための最も合理的な戦略だと思っています。
「何歳からでも逆転できる」は、残念ながら幻想だと思う
たまに「カーネル・サンダースだって60歳から成功した」と言われますが、実際の彼らは若い頃からずっと動いていた人です。
成功は、突然やってくるものではありません。
僕も同じで、20代からずっと動き続けてきた結果が今に繋がっている。
もしあの時、「もう少しプライベートを大事に」なんて言っていたら、今のように時間を自由にコントロールする働き方はできていなかったと思います。
“何歳からでもチャレンジできる”のは事実です。
でも、“同じ規模のチャレンジができる”わけではない。
過去にどれだけリスクを取ってきたかが、次の挑戦のサイズを決める。
これは経営でも投資でも、人生でもまったく同じです。
人生単位で考える「バランス」とは
僕が思う「本当のワークライフバランス」は、1日の配分ではなく、人生全体の時間戦略です。
20代で体力を全投入。
30代で技術を磨き、
40代で人脈を広げ、
50代で健康を維持しながらレバレッジをかける。
この流れを意識してきた結果、今は昔より短い労働時間でも成果が出せるようになったと思っています。
まさに「量の投資が、質の自由を生んだ」と感じています。
最後に:バランスより「駆け引き」を
20代で体力を出し切るのは、苦しいです。
でも、その“駆け引き”を制した人だけが、後の人生で“短く働いても結果を出せる自由”を得られる。
バランスを取るのではなく、いつどこでリソースを投下するかを考える。
それが僕の経験上、人生を豊かにする一番の戦略です。
🔹まとめ
-
若い時は「量」こそ最大の投資。
-
年齢ごとに武器(体力→技術→人脈→健康)が変わる。
-
ワークライフバランスは“均等”ではなく“駆け引き”。
-
何歳からでも挑戦できるが、規模は過去の努力量で決まる。
-
人生単位で“時間の配分”を設計することが、真の自由につながる。
少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。