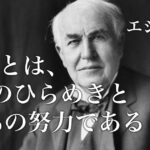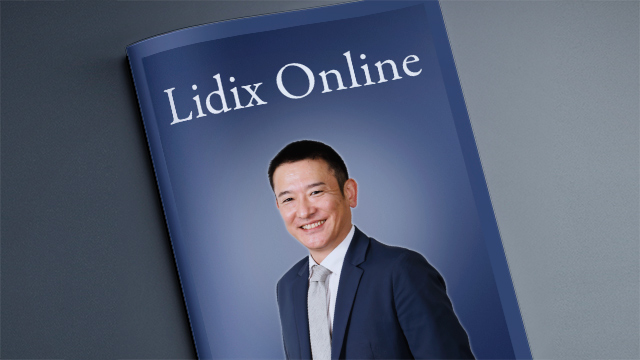星野リゾートに学ぶ「教科書経営」──逆境をチャンスに変えた3つの軸
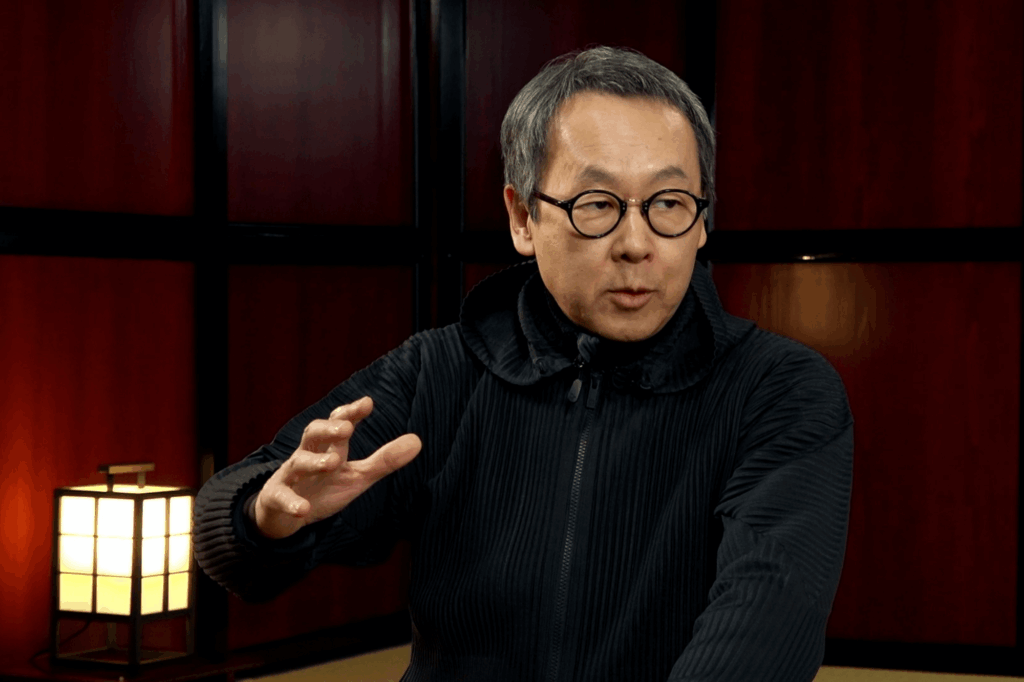
先日、星野リゾート代表の星野佳隆さんが出演している対談動画を2本続けて見ました。
どちらも切り口は違うものの、共通して浮かび上がってきたのは、
-
「経営学の教科書通りにしかやらない」
-
「父との対立と追放劇」
-
「ビジョン設定と人材確保」
-
「インターネット・AI時代への適応」
という、ひとつの企業をまったく別のステージに引き上げた“物語”でした。
今回は星野リゾートの成功を支えた本質を、自分なりに整理をしてブログにまとめます。
1. 教科書通りにしかやらない経営者
星野さんの一番の特徴は、徹底した「教科書信仰」です。
-
自分の直感は信用しない
-
「なんとなくピーンときた」は封印
-
判断の根拠はすべて、世界中の教授が書いた論文・経営学の教科書
という、ある意味とても“ドライ”なスタンスです。
観光業界では「教科書通り」がむしろレア
面白いのは、観光・旅館業界では、こうした“理論ガチガチ”の経営者がほとんどいなかった、という点。
だからこそ、
「教科書通りにやる」=それだけで競争優位になる
という、逆説的な状況が生まれていたわけです。
教科書があるから、ブレずに継続できる
もうひとつ印象的だったのが、
うまくいってないときでも、教科書通りにやっていれば「いつか成果が出る」と信じて続けられる
という話。
私もそうですが、独自路線だと、結果が出ないとすぐ不安になって「やっぱりダメかも」と路線変更してしまいがちです。
そうすると、本当はあと一歩でブレイクスルーだったかもしれないのに、そこでやめてしまうリスクがある。
教科書のセオリーを軸にしているからこそ、
「結果が出るまで、しつこく続けられる」─ここが非常にリアルだなと感じました。
2. 父との決裂と追放劇が生んだ“本気度”の証明
星野リゾートの物語で外せないのが、父との対立と追放劇です。
社員のやる気は「誰の責任か?」
対立の本質は、時代によって変わった“人材観”でした。
-
父の時代(高度経済成長期)
→ やる気のない社員の責任は「社員本人」。 -
星野さんの時代(90年代以降)
→ やる気のない社員がいるのは「経営者の責任」。
教科書でも、60~70年代と90年代以降では、人材論が180度ひっくり返っているそうです。
星野さんは、dsf
優秀な人材に来てもらうための努力をするのは経営者側
働く環境を整え、きちんと評価し、報酬も含めて「残りたくなる会社」にするのが責任だ
という立場。一方で、父は昔ながらのワンマンスタイル。
結果、1989年ごろに完全に対立し、会社から“追放”されます。
追い出されたことで、むしろ「本気」が伝わった
本人の言葉で印象的だったのは、
追放されたことで、改革を望んでいた社員たちに「星野は本気だったんだ」と伝わった
という部分。
「中途半端に折り合いをつけて残る」のではなく、一度会社から出されたことが、
改革派としての覚悟を社員に示す結果になったというのは、皮肉でもあり、ドラマでもありますね。
株主が引き戻し、役割を再設計
その後、教科書通りの経営方針に賛同した社外株主たちが中心となり、
-
株主総会での“ギリギリの勝負”を経て復帰
-
父をいったん経営から外しつつ、のちに会長として対外的な役割にシフト
という形で、“経営の対立”と“親子関係”の両方に決着をつけました。
ここにも、
感情で物事をねじ伏せない。
役割分担を変えることで、関係性をリデザインする。
という「教科書的で、かつ現実的」な視点がにじんでいます。
3. 地方の古い旅館から、優秀な人材はどう集めたのか?
復帰後に待っていたのは、絶望的な採用難だったそうです。
-
古い建物(40年以上)で、特に魅力的でもない
-
休みは少ない、給料は安い
-
土日も年末年始も仕事
-
立地も地方(軽井沢)
これで学生に「ウチに来ませんか?」と言っても、当然ながら誰も来ない。
最初の2年は「採用ゼロ」
リクルートの合同企業説明会に出ても、
-
隣の製造業には学生がどんどん座る
-
星野リゾートのブースはガラガラで、椅子を融通し合うレベル
-
2年間、採用ゼロ
という、かなりしんどいスタートだったそうです。
教科書通りに「ビジョン」を語る
ここで星野さんが選んだのは、やはり“教科書通り”。
経営者が最初にやるべき仕事は、事業ドメインと数値目標を含んだビジョンを設定すること
というセオリーに沿って、明確なビジョンを打ち出します。

ビジョン:「リゾート運営の達人になる」
ここで「所有・開発」からは一歩引き、あくまで運営に特化する(運営特化戦略)という事業ドメインを明確化。
さらに「達人」の条件として、
-
顧客満足度
-
収益率(GOP 20〜30%)
-
社員満足度
の3つを同時に満たす、という数値付きの目標を掲げました。
「今の条件」ではなく「20~30年後の未来」を売る
当時の条件だけを説明しても、誰も来てくれない。
だからこそ、
20年後・30年後には、世界中に星野リゾートがあるかもしれない。
その立ち上げメンバーにならないか?
という、未来の絵を語ることに全振りしたそうです。
その結果、3年目にようやく2人がブースに来てくれたとき、星野さんは「名前を聞く前に」「履歴書を見る前に」即決で口説きにいったとか。
ここには、
-
現状の条件では戦えない
-
だからこそ、ビジョンとストーリーで勝負するしかない
という、スタートアップ的な感覚も感じます。
4. 「運営特化戦略」という逆張りのビジネスモデル
1990年代初頭、日本はバブル崩壊へ。
-
需要は伸びない
-
供給過剰(部屋の数>お客さんの数)
-
多くのリゾートが経営難
という中で、星野リゾートが選んだのが、
「所有・開発」のリスクは負わず、運営だけに特化する
というビジネスモデルでした。
当時の日本のホテル・旅館業界には、ほとんど例がなかったスタイルです。
ダメなホテルを「なぜダメか?」からやり直す
再生の現場でも、アプローチはあくまで教科書通り。
-
まず現場の社員と一緒に「なぜダメなのか」を徹底的に共有する
-
「それでも来てくれているお客様」は誰なのかを分析
-
その層のニーズに、資源を一点集中して応えていく
たとえばリゾナーレ八ヶ岳では、
-
「首都圏から車で2時間半以内」
-
「12歳以下の子ども連れファミリー」
という、明確なターゲットに絞り込み、そこに向けてコンセプトとサービスを再設計したそうです。

成功から、投資家とのパートナーシップへ
自分たちのリスクでこうした再生を成功させた結果、
-
ゴールドマンサックスなどの投資家から、運営だけを任される案件が増える
-
所有リスクを負わずに、運営による収益を積み上げるモデルが確立
という流れにつながります。
伝統的な家業から、「運営のプロフェッショナル集団」への転換。
ここでもやはり、軸になっているのは教科書のセオリーです。
5. インターネットとAI時代:ブランドではなく「AIに選ばれるか」
話は現在に飛びます。
予約は紙からネットへ
1990年代中盤から、宿泊予約はインターネットに移行。
「インターネット上でどうやって予約を取るか?」
が、新たな勝負どころになりました。
星野リゾートは、予約や滞在の自由度を高めるシステムに今も大きな投資をしており、2025年末〜2026年にかけて新システムを導入予定だそうです。
AI時代、「ブランドは通用しなくなる?」
さらに星野さんは、
AIの時代には、ブランドは通用しなくなる
とかなり踏み込んだ見方をしています。
AIは、
-
無限の記憶力
-
先入観のないロジック
-
ユーザーの「こういう旅がしたい」という要望
をもとに、最適な宿をおすすめしてくる。
そのとき、必ずしも有名ブランドが選ばれるとは限らないというわけです。
だからこそ、次の戦いは
「どうやったらAIに選んでもらえるか?」
にシフトしていく、と。
これもまた、「ブランド力」頼みの発想ではなく、環境変化を前提に、勝ちパターンを組み替えていく教科書的な姿勢だと感じました。
これは私の事業でも参考になる考え方だと思いました。
6. なぜ“伝統的な経営”を捨ててまで、教科書に賭けたのか?
ここまでの流れを整理すると、星野リゾートが「伝統的な家業的経営」を捨ててまで、教科書通りの経営に舵を切った理由は、大きく4つにまとめられます。
-
経営環境の大転換
-
バブル崩壊、人口減少、供給過剰
-
「勘と経験」では生き残れないと判断
-
-
人材環境の変化
-
社員が会社を選ぶ時代へ
-
「やる気のない社員=経営者の責任」というパラダイム転換
-
-
自分の感覚への不信と、科学的根拠への信頼
-
自分の勘ではなく、世界の経営学者の知見をベースにする方が納得できる
-
教科書通りであれば、成果が出るまで継続できる
-
-
業界的に“教科書通り”がレアだったこと
-
伝統的な旅館業界だからこそ、セオリーを徹底するだけで優位に立てた
-
要するに、
「時代が変わった」のに、
「やり方を変えない」のは、経営者の怠慢である。
という、かなり厳しい自己認識からスタートしている、と感じます。
7. まとめ:荒野を進む探検隊の「地図」と「仲間」
最後に、星野リゾートの物語を、自分なりに一言でまとめると、
教科書=地図、ビジョン=目的地、人材=一緒に歩く仲間
この3つを揃えたからこそ、古い地方旅館という事業から、世界に通用する「運営の達人集団」へと変貌できたのだと思います。
-
地図(教科書)があるから、迷わず進める
-
目的地(ビジョン)があるから、厳しい道でも人が集まる
-
仲間(人材)がいるから、現場の細かな問題を仕組みで解決し続けられる
家族内の対立や追放、採用ゼロの時代、バブル崩壊、AI時代への突入──
こうした逆境をすべて「前提」として受け止め、セオリーとビジョンを武器に、しつこく進み続けた企業のケーススタディとして、星野リゾートの物語は、今の経営者にとって相当学びが深いな、と感じました。
自分の直感や経験ももちろん大事ですが、
「世界中の教科書を素直に信じて、まずは丸パクリでやってみる」
という姿勢を一度、本気で取り入れてみてもいいのかもしれません。
今回も勉強になりました。