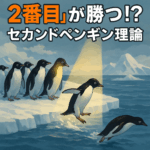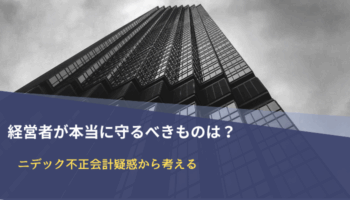「今期の利益、たくさん出てるのに、なぜか会社にお金が残らない…」
そんな悩みを抱えている経営者の方、いらっしゃいませんか?実はこれ、多くの会社で起こりがちな「あるある」です。
税理士から「利益が出ましたよ!」と報告されても、手元に現金がなければ困ってしまいます。
今回は、その「利益が出ているのに現金が残らない謎」を、分かりやすく解説していきます!
利益とお金は別物!基本を知ろう
まず、重要なポイントは「利益」と「現金(お金)」が必ずしも同じではない、ということです。
私たちがよく目にする「損益計算書(PL)」は、1年間の会社の売上と費用を計算して、最終的な利益を示すものです。一方で、「貸借対照表(BS)」は、ある特定の時点での会社の財産(資産)、借金(負債)、そして純粋な財産(純資産)の状態を示すものなんです。
この2つの書類を合わせて見ることが、お金の流れを理解する上で非常に重要です。
なぜ利益が出ているのにお金がないのか?2つの大きな理由
ズバリ、その主な原因は以下の2つに集約されます。
- 資産が増えているから
- 負債が減っているから
「え?資産が増えるのは良いことじゃないの?」そう思われたかもしれません。しかし、実はこれが現金減少の大きな要因となるのです。
順番に見ていきましょう!
1. お金が「資産」に変わっているパターン
利益は出ているのに、そのお金が「現金」として手元に残らず、形を変えて「資産」になっているケースです。
- 役員貸付金・従業員貸付金(会社のお金をプライベートで使った) 社長や従業員が会社のお金を個人的な支払いに使ってしまうと、それは「貸付金」という会社の「資産」になります。経費にはならないため利益は減りませんが、現金は会社から出ていってしまいます。銀行が最も嫌う処理の一つとも言われています。
- 売掛金(まだ回収できていない売上金) 商品やサービスを提供し、売上が計上されても、その代金がまだ入金されていない場合、「売掛金」として「資産」に計上されます。売上は利益に貢献しますが、現金はまだ手元にないため、資金繰りが苦しくなります。
- 在庫(仕入れたけれどまだ売れていない商品) 仕入れに多額のお金を払っても、その全てが期末までに売れていない場合、売れ残った分は「在庫(商品)」として「資産」になります。お金は出ていっているのに、経費になるのは売れた分だけなので、利益は減らず、現金だけが減ってしまいます。
- 前払費用(先に支払った来期の経費) 数ヶ月分の広告費などをまとめて前払いした場合、支払ったお金の全額が今期の経費になるわけではありません。来期以降の経費となる部分は「前払費用」という「資産」として計上されるため、お金は出ていくのに、今期の利益は減らない、という状況になります。
- 車両・固定資産(一括で購入した高額なもの) 例えば600万円の車を一括で購入した場合、支払いは600万円ですが、経費になるのは「減価償却費」として毎年少しずつ(例えば100万円ずつ)計上される分だけです。残りの500万円は「車両運搬具」という「資産」になるため、お金は大きく減っても、今期の利益への影響は限定的になります。
- 投資有価証券(株式や投資信託など) 会社の資金で株式や投資信託などを購入した場合、それは「投資有価証券」という「資産」になります。お金は会社から出ていきますが、経費にはならないため、利益には影響せず、現金だけが減ります。
- 積立型生命保険(保険料の一部が資産に) 生命保険の中には、掛け捨て部分と積立部分があるタイプがあります。積立部分の保険料は「保険積立金」として「資産」になるため、お金は払っていても経費として全額は計上されず、利益は減らないのに現金は減る、という状況になります。
- 敷金(返還される預け金) オフィスの賃貸契約などで支払う敷金は、基本的には退去時に返還される性質のお金なので、「差入保証金」という「資産」になります。経費にはならないため利益は減りませんが、多額の現金が出ていくことになります。
つまり、「資産が増える」ということは、現金が別の形に姿を変えただけで、手元からはなくなっている状態なのです。
2. 「負債」の返済でお金が減っているパターン
利益が出ているのに現金がないもう一つの大きな理由は、過去の借金や未払い金を返済しているからです。負債が減るということは、それだけお金が出ていっていることを意味します。
- 買掛金の返済(仕入れ代金の支払い) 例えば昨年の12月に仕入れた商品の代金が、今年1月に支払われる場合。その仕入れは既に昨年の経費として計上されていますが、お金の支払いは今年行われるため、今年の利益には影響しないのに現金だけが減ります。これは「買掛金」の減少として処理されます。
- 未払金の支払い(過去の経費の支払い) 広告費など、昨年の経費として計上済みだが、支払いは今年になった場合も同様です。今年の利益には影響しないのに、現金だけが減ります。これは「未払金」の減少として処理されます。
- 預かり金の支払い(源泉徴収税の納付など) 従業員や業務委託者から預かっていた源泉徴収税(所得税など)を、会社がまとめて税務署に納付する際にも現金が出ていきます。これはあくまで預かっていたお金を支払うだけなので、会社の経費にはなりません。
- 借入金の返済(元本の支払い) これが最も多い、お金が減る理由かもしれません。銀行からの借入金を返済する際、利息部分は経費になりますが、元本の返済は一切経費になりません。例えば1,000万円利益が出ても、借入金の元本を1,000万円返済していたら、手元の現金は増えない、という状況になります。
このように、「負債が減る」ということは、過去の義務を果たしているだけで、利益とは関係なく現金が出ていっている状態なのです。
横領も要注意!
ちなみに、これらの会計上の理由以外に、シンプルに「社内で横領されている」という可能性も指摘されています。利益は出ているはずなのに現金がない、という場合、真っ先に疑われる理由の一つとのことです。信じたくはありませんが・・・。
まとめ:「貸借対照表」を見る癖をつけよう!
利益が出ているのに現金が残らないのは、会計上の「資産の増加」や「負債の減少」が原因であることがほとんどです。
- 資産が増えれば増えるほど、資金繰りは悪化する。
- 負債が減れば減るほど、資金繰りは悪化する。
逆に、「負債は借りられるだけ借りた方が現金が増える」という考え方もあるのです。
自社の資金繰りをしっかり把握するためには、損益計算書(PL)だけでなく、貸借対照表(BS)を過去のデータと比較して見ることが非常に重要です。資産や負債がどのように増減したかを確認することで、お金が増えない、あるいは増えた理由が明確になります。
決算書は一見難しそうですが、今回紹介したような基本的なルールを少しずつ理解していくことで、会社の「今」と「未来」が見えてくるはずです。ぜひ、自社の決算書を分析して、経営改善に繋げてください。